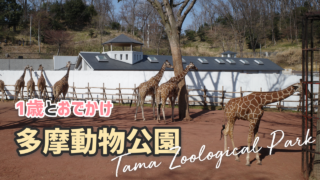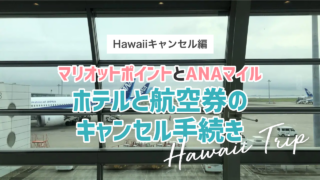承認と成長のバランス
技術の世界では、評価されることと成長することのバランスが難しい。
特に今の時代、SNSやコミュニティでちょっとしたことでも「すごい!」「天才!」と簡単に持ち上げられる(本当に思っているのかも不明)。
承認は人間の基本的な欲求だし、モチベーションになるのは確かだ。でも、技術が未熟な段階での過度な称賛は諸刃の剣だとも思う。
「すごい」と言われ続けると、どうしても現状に満足してしまう。自分はもう十分だと錯覚して、本来必要な苦労や試行錯誤をショートカットしようとする。そして気づいたときには、同期や後輩に追い抜かれている。
適切なフィードバックとメタ認知が大事だ。「〜〜さんすご〜い!」とほめられるだけの環境では、早めに腐って頭打ちしてしまう。この時代だからこそ、根気強く頑張る姿勢が必要なんだと思う。
スクール・指導者と“生徒”の関係性
スクールやコミュニティ、指導者のやり方によっては、この問題をさらに複雑にすることがある。「成功した卒業生」は最高の宣伝材料だ。「うちの卒業生がこんなすごいサービスを作りました!」「卒業後3ヶ月でこんな企業に就職!」と、まだ未熟な段階からその人を持ち上げることが多い。
生徒の成長を純粋に願う一方で、ビジネスとしての成功も必要とする。その結果、生徒を過度に持ち上げてしまうことがある。
本人も最初は嬉しいんだよね。自分がスクールの看板として扱われること、その気持ちよさに酔ってしまうこともある。でも数年後、本当に技術を磨いた段階で振り返ると「あんなに持ち上げられて、でも実際はまだ全然だった」と恥ずかしく感じることもある。
良いスクールと良くないスクールの違い
技術が身に付く良いスクール、指導者とは。
ほめて持ち上げるだけでなく「しっかりとフィードバックしてくれること」だと思う。生徒の現状を客観的に伝え、具体的な改善点を示してくれる指導者は、本当の意味で生徒の成長を支えている。
「これはいいけど、ここは改善が必要」「この部分は業界標準からするとまだまだ」といった正直なフィードバックは、その瞬間は少し痛いかもしれないけど、長い目で見れば生徒の財産になる。
一方で、よくないスクール・指導者は自社の営利目的のために持ち上げるだけ持ち上げて、本人の技術者としての成長を阻害してしまう。生徒に「あなたはもう十分すごい」と思わせることで、厳しい学習の過程をスキップさせてしまう。それは短期的には気持ちいいけど、長期的には成長の機会を奪ってしまう。
真の成長へ向けて
真の技術力は、称賛の言葉ではなく、壁にぶつかり、それを乗り越えた経験から生まれるのではないか。「ここがダメだ」「もっとこうした方がいい」という的確なフィードバックがあってこそ、技術は磨かれていく。
メタ認知、つまり自分を客観的に見る能力が重要だ。自分が本当にどのレベルにいるのか、何が足りないのか、業界全体の中での自分の立ち位置はどこなのか。そういう冷静な自己分析ができる人は、「すごい」の罠に落ちることなく成長し続けられる。
この時代、簡単に情報を得られて、簡単に称賛も得られる。だからこそ、あえて遠回りする勇気、批判を受け入れる謙虚さ、そして日々コツコツと技術を磨く根性が必要なんだと思う。
華やかな称賛よりも、適切な批判と厳しい自己分析。それが技術者としての長い道のりで、本当に自分を成長させるものだと信じている。